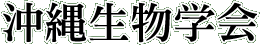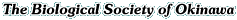(2) 過去の大会のプログラム

沖縄生物学会第52回大会の開催のお知らせと講演プログラム
沖縄生物学会の第52回大会を下記の要領で開催いたします。今大会は口頭発表14題、ポスター発表28題(小学生1題、高校生9題、一般18題)、そして特別パネル展示『沖縄の潮間帯現状報告:「沖縄の潮間帯―1974」との比較』を予定しております。また、本年度大会の公開シンポジウムは、『琉球列島の「隠れた」環境における生物多様性』と題しまして、隠れた環境でたくましく生息している海の生き物についての発表を予定しております。さらに、第6回池原賞の受賞式もあります。多数の方のご参加をお待ち申し上げております。
沖縄生物学会 第52回大会: 2015年 5月30日(土) 沖縄国際大学 5号館1階
大会日程 (大会参加費:1,500円、学生1,000円、 懇親会費:3,000円 学生1,000円)
| 5月30日(土) | 受付 | 8:30~ | 沖縄国際大学5号館ロビー |
| 沖縄国際大学 | 一般講演 | 9:00~12:00 | 沖縄国際大学5号館107教室 |
| 休憩(昼食) | 12:00~13:00 | ||
| 総会 | 13:00~13:45 | 沖縄国際大学5号館107教室 | |
| 第6回池原賞表彰式 | 13:45~14:15 | 沖縄国際大学5号館 107教室 | |
| 小学生ポスター発表 | 14:15~14:30 | 沖縄国際大学5号館1階ロビー | |
| 一般ポスター発表 | 14:30~16:00 | 沖縄国際大学5号館1階ロビー | |
| 一般講演 | 16:00~16:45 | 沖縄国際大学5号館107教室 | |
| 公開シンポジウム | 16:50~18:20 | 沖縄国際大学5号館107教室 | |
| 理科教育連携ミニシンポジウム | 16:00~18:20 | 沖縄国際大学5号館106教室 | |
| 懇親会 | 18:30~ | 沖縄国際大学厚生会館4階オキラクカフェ |
プログラム
一般講演【午前の部 9:00~12:00】 5-107教室
O-01: リュウキュウツヤハナムグリをだまして利用するボウランの繁殖戦略
○新垣則雄(沖縄農研)・安田慶次(沖縄森資研)・金山祥子・實野早紀子・若村定雄(京都学園大)
O-02: 沖縄島北部やんばるにおけるイルカンダの訪花者
○小林 峻(琉球大院・理工/JSPS特別研究員DC1)・傳田哲郎(琉球大・理)・宇井大晃(琉球大院・理工)・伊澤雅子(琉球大・理)
O-03: 琉球列島と台湾のヒメサギゴケにおける系統地理学的研究
○梅本巴菜(茨大院・農,科博・植物)・中村 剛(北大・植物園)・横田昌嗣(琉球大・理・海洋自然)・國府方吾郎(科博・植物,茨大院・農)
O-04: 沖縄島に生育するボチョウジ属の分枝発生パターンに関する数理モデルについて
渡利正弘(沖縄工業高等専門学校・総合科学科)
O-05: 地域の環境問題を教材とした中学3年理科「自然環境と人間のかかわり」の授業実践
○飯田勇次(唐津市立海青中講師・玄海地区海藻研究会)・片山舒康(生物教育研究所)
----- 休憩 10:15~10:30 -----
O-06: ハナヤサイサンゴの初期発生段階における緑色蛍光タンパクの分布変化
○ Dwi Haryanti(琉球大院・理工・海洋環境)・日高道雄(琉球大・理・海洋自然)
O-07: 熱帯性海洋生物の分布境界の形成要因を探る-島嶼沿岸域の海洋ベントスの事例-
○井口 亮(沖縄高専・生物資源)・中島祐一(OIST・海洋生態物理学ユニット)
O-08: 沖縄島における戦後の海岸の利用と変化について:「沖縄の潮間帯-1974」追跡調査(2014)と関連して
○佐藤崇範(琉球大・国際沖縄研究所)・水山 克・仲栄真礁・河村伊織(琉球大院・理工)
O-09: 西表島北西部におけるウミショウブ群落間の種子交流に関する数値解析
○村上智一(防災科研)・河野裕美(東海大沖縄)・玉本 満(東海大海洋)・水谷 晃・下川信也(防災科研)
O-10: 蝶の翅の発生過程のリアルタイム・イメージング
○岩田大生(琉球大院・理工)・大瀧丈二(琉球大・理)
O-11: 民生用のデジカメを用いた安価な顕微鏡微速度撮影と高速度撮影法
○泉水 奏(琉球大・医・人体解剖学講座)
----- 休憩(昼食)12:00~13:00 -----
総会【13:00~13:45】 5-107教室
第6回池原賞 受賞式【13:45~14:15】 5-107教室
研究奨励部門:中西 希氏
教育功労部門:沖縄生物教育研究会
ポスター講演(小学生・高校生)【14:15~16:00】 5号館ロビー
P-01: ケラマジカの体の毛について(14:15~15:00)
前田琳華・鹿島匠人・糸嶺航生・前田涼華・細川教子(慶留間小)・遠藤 晃(南九州大)
P-02: 沖縄本島西屋部川におけるネッタイテナガエビの分布と成長に関する研究
北村育海(名護高校生物部)
P-03: 田嘉里川におけるオキナワヒゲナガカワトビケラの生活史Ⅱ
○新垣夏実・○金城実希・○仲村勇人・伊是名良平・稲福 凛・町田佳生莉(辺土名高校)
P-04: ビオトープぱはらの研究 ~水生生物相と変遷~
金城幸輝(辺土名高校環境科サイエンス部)
P-05: チョウを用いた環境調査
比嘉莉菜・新田有佳子・濵田愛衣・照屋匠未・嶋倉紗羽(球陽高校)
P-06: 沖縄の植物に含まれる物質の紫外線吸収率
上原勇太・江頭 俊(球陽高校)
P-07: 安謝川の生物相調査
○喜屋武慧悟・玉城 武・儀間 大・松川祐太朗・佐渡山郁太(浦添高校・サイエンス部)
P-08: ガジュマルFicus microcarpaの研究Ⅱ ~花嚢と生きる小さなハチ達~
○玉城 武・喜屋武慧悟・儀間 大・松川祐太朗・佐渡山郁太(浦添高校・サイエンス部)
P-09: 沖縄島に生息するオオムカデ属の種構成と分布
仲間信道・宮里美穂(普天間高校)
P-10: 普天間高校に生息するアリの種構成と分布
久髙愛実・呉屋昇太・垣花辰紀・安里和之・山内梨乃香(普天間高校)
ポスター講演(一般)【14:30〜16:00】 5号館ロビー
P-11: 網羅的プロテオーム情報解析によるヒト特異的アミノ酸配列の探索
○津波古昌和(琉球大院・理工・理工)・大瀧丈二(琉球大・理)
P-12: 琉球列島におけるヤブランの倍数性と生育環境の選好性
○石川伊智子(琉球大院・理工)・横田昌嗣・傳田哲郎(琉球大・理)
P-13: 非造礁性サンゴ,イボヤギ(Tubastraea)の垂れ下がりポリプ
○山城秀之(琉球大・熱生研・瀬底研究施設)
P-14: サンゴの教材化の可能性を探る―アザミサンゴを用いた実験実習を通して―
○仲栄真礁(琉球大院・理工・海洋環境)・日高道雄(琉球大・理・海自)
P-15: 枝状ミドリイシの群体形に及ぼす水流の影響について
山本広美(美ら島研究センター)・政木清孝・富永昇・磯村尚子(沖縄工高専)
P-16: ナマコの種分化と生殖隔離に関与しうる精子の走化性の関連の検討
○白幡大樹 (琉球大院・理工)・守田昌哉 (琉球大)
P-17: mt DNA解析によるタカサゴの遺伝的集団構造と個体群動態
○賀数大吾(琉球大院・理工)・張 至維(台湾國立海洋生物博物館)・立原一憲・今井秀行(琉球大・理)
P-18: 中城湾沿岸域に出現する魚卵の種判別マーカー作成の試み
○川口 亮・石田 肇・木村亮介(琉球大・医)・桜井 雄(沖縄環境調査(株))・昆 健志(琉大研究推進)・井上 潤(OIST)・石森博雄(いであ(株))
P-19: 西表島網取湾ウダラ川汽水域に優占する魚類の分布とそれに関わる塩分動態
井上太之(東海大・沖縄)・村上智一(防災科研)・南條楠土(水大校・生物生産)・河野裕美(東海大・沖縄)
P-20: 北限分布域の西表島におけるウミショウブEnhalus acoroides の生活史
玉本 満(東海大・海洋)・水谷 晃・崎原 健・河野裕美(東海大・沖縄)
P-21: 西表島北西部のウミショウブ群落におけるアオウミガメの食痕分布とその影響
川田菜摘(東海大・海洋)・崎原 健・水谷 晃・井上太之(東海大・沖縄)・村上智一(防災科研)・河野裕美(東海大・沖縄)
P-22: 浦添市港川海岸に生息するウミウシ類の季節消長
具志佑莉香・真座美来・○山川彩子(沖縄国際大・地域環境)
P-23: スポットライトセンサスによる座間味村阿嘉島におけるケラマジカの生息実態」
○遠藤 晃(南九州大)
P-24: 西表島におけるカンムリワシのルートセンサスの精度検証
○水谷 晃(東海大・沖縄)・福田 真・阪口法明(環境省)・河野裕美(東海大・沖縄)
P-25: 沖縄島におけるイソヒヨドリの環境利用について
○宇井大晃(琉球大院・理工)・伊澤雅子(琉球大・理)
P-26: 自動撮影装置によって確認された西表島の鳥類相
○中西 希・伊澤雅子(琉球大・理)
P-27: ヤンバルクイナ・ノグチゲラ・アカヒゲの沖縄島北部地域における分布南限
に関する調査
宮城誠也・新垣裕治(名桜大・国際・観光産業)
P-28: 国頭村の県道70号線沿い(県道2号との交差点~楚洲集落)のヤンバルクイナ見学者に関する調査
新垣裕治・津嘉山実結(名桜大・国際・観光産業)
特別パネル展示【14:30〜16:00】 5号館ロビー
沖縄の潮間帯現状報告:「沖縄の潮間帯―1974」との比較
沖縄の潮間帯調査ワーキンググループ 水山 克・仲栄真礁・河村伊織・佐藤崇範
1974年、西平守孝博士は、本土復帰直後の沿岸部開発により失われていく潮間帯およびその生物相を、本島全域にわたって調査しました。そして1985-86年に行われた再調査では、およそ10年間で人為的攪乱が進行し、ほぼ全調査項目において状況が悪化したことが報告されました。
そこで本研究では、沖縄島の潮間帯における人為的環境撹乱の現状(2014-15)を明らかにし、1974年および1985年に行われた調査結果と比較することによって、40年間で各調査地点がそれぞれどのように変化したのかを明らかにしたいと考えています。今回は1974年に西平博士によって撮影された各調査地点の景観写真と、それと同じアングルで撮影された2014年の景観写真を展示し、沖縄の海岸域における40年の変化について展示します。
一般講演【午後の部 16:00〜16:45】 5-107教室
O-12: 西表島で確認された日本初記録科となるガムシ上科Spercheidae科の1種とその生息環境○北野 忠(東海大・教養)・河野裕美(東海大・沖縄)・多比良嘉晃(静岡市)
O-13: 交通事故から初めて野生復帰したイリオモテヤマネコの追跡
○日名耕司・田口麻子・関東準之助・早川玲子・福田 真(西表野生生物保護センター)
O-14: 水納島と奄美大島のジャコウネズミは本当に絶滅したのか?
○中本 敦(琉球大・大教セ)・中西 希(琉球大・理)
公開シンポジウム【16:50〜18:20】 5-107教室
シンポジウムタイトル:琉球列島の「隠れた」環境における生物多様性
コンビナー: 成瀬 貫・安田直子
琉球列島では比較的小さな空間に多様な環境が存在しており,それが多様な生物の生息を可能にしている一因であることが考えられます.琉球列島の生物について様々な研究が続けられていますが,人間にとって厳しい環境条件や注目度の低さから,あまり調査が行われていないような環境も多々あります.そこで今回,最近調査が行われるようになってきた,人の目に触れにくい環境で生息している生物についての研究成果を紹介します.
水山克ら: 沖縄島西海岸における中深度サンゴ礁生態系に関する研究
藤田喜久: 琉球列島の海底洞窟に生息する無脊椎動物相について
安田直子: 内湾的環境に生息するイシサンゴ類の生態について
成瀬 貫: 潮下帯砂泥底に生息する穴居性甲殻類について
懇親会【18:30〜】厚生会館4階オキラクカフェ
公開シンポジウム終了後、大学内の厚生会館4階のオキラクカフェにて懇親会を予定しております。講演時間内に出来なかった討論や会員同士の親睦をより深めるため、是非ご参加下さい。
大会関連集会
理科教育連携ミニシンポジウム【16:00〜16:40】 5-106教室
昨今、沖縄の小・中・高等学校における生物教育が、指導者の絶対数や力量の不足により低迷しているのではないかという懸念が、高校生物教師の間で話題に上ることがある。特に中学・高校では受験指導に力点が置かれすぎて生物が暗記科目になっているのではないかなど、簡単には解決できない問題が実例をもって語られる。また、新教育課程が2012年より導入され、遺伝子関連分野の単元が大きく増えたことで、実験・観察等ができにくくなっているという現状がある。
一方で、生物(理科)指導者のスキルをアップするような手だてが、県主体ではほとんど行われていない。この現状認識を沖縄生物教育研究会と沖生会が共有し、よりよい生物教育とは何なのか、子どもたちのためになる授業づくりに必要な手だては何なのか、を考えていくのが昨年発足した理科教育連携WGの趣旨である。
今回のミニシンポジウムはその手始めとして、理科教育連携WGの意義や目的を共有することや、沖縄の生物を使った教材の開発に向けた情報交換、今後の活動計画の検討などを予定している。堅苦しく考えず、気軽に高・大の生物教育関係者が交流できる場としたい。
タイムスケジュール
- 沖縄の生物教育・現状報告(10分)
- 沖縄の生物を使った教材開発の例(10分)
- パネルディスカッション&フリートーク(20分)
義務教育:知花史尚(県総合教育センター主事)、高校:儀間朝宜(浦添高校)
山﨑仁也(県博物館・美術館)、富永 篤(琉球大学)
討論者:藤田喜久(県芸大)、杉尾幸司(琉大)、知花史尚、儀間朝宜、
県教育庁理科担当:未定、若手研究者:仲栄真礁
司 会:山﨑仁也